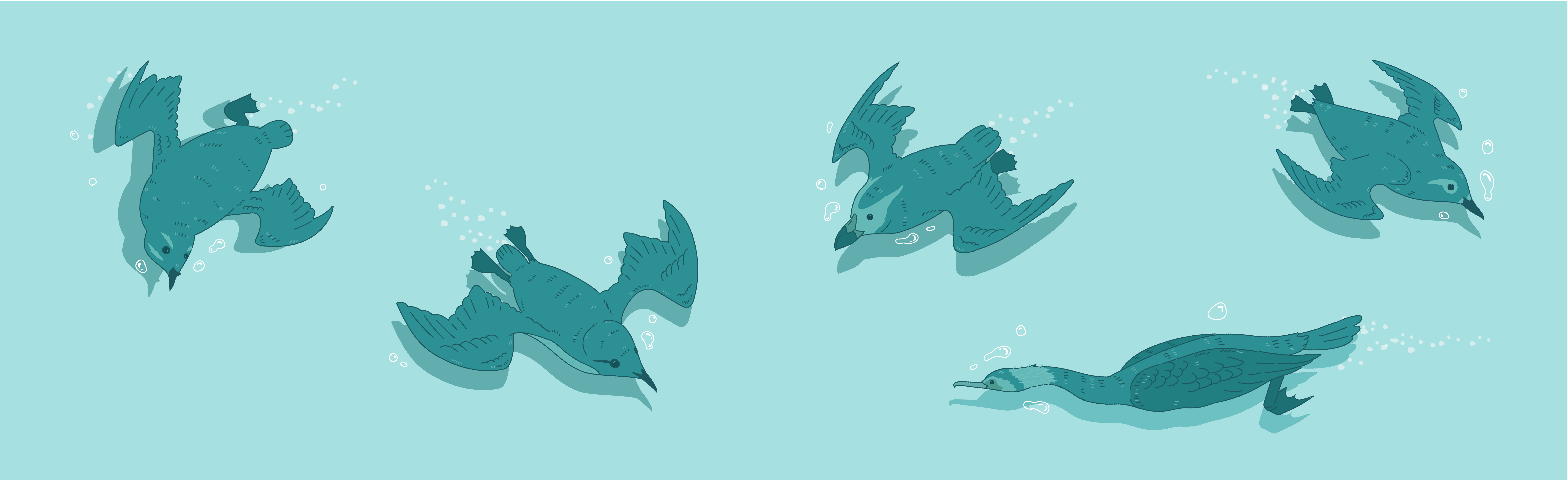黒田賞受賞記念講演
2025年度日本鳥学会黒田賞受賞者:岡久雄二(人間環境大学)
日時:9月14日(日)14:30〜15:30
会場:3号館・41番教室
科学と実務をつなぐ保全鳥類学の実践
本講演では、私がこれまで取り組んできた鳥類を対象とする保全生物学の研究と、その成果を社会実装に結びつけた実践活動について報告する。主たる対象種は、トキやアカモズをはじめとする国内希少野生動植物種である。私は、これらの種における生息域内保全と生息域外保全の統合的戦略(いわゆるワンプランアプローチ)の構築と、保全策への科学的貢献をテーマとしてきた。
トキに関しては、環境省の野生生物専門員としての在職中から現在に至るまで約10年にわたって佐渡島における野生復帰事業に携わり、放鳥個体群の科学的評価に基づいて保全施策を推進してきた。特に、学術面では、育成方法と繁殖行動の関連を分析した研究、統合個体群モデルによる復帰評価手法の開発、さらには野生復帰による地域経済波及効果などを発表してきた。これらの成果は、私自身が保護増殖事業の計画管理やモニタリングの設計、科学的効果検証、地域との合意形成まで、多様な実務に反映してきた。そして、多様な関係者とともに科学的評価に基づく順応的管理を推進することで、トキの野生復帰は成功した。
アカモズについては、2022年より保護増殖プロジェクトを組織し、長野県を中心とした生息域内外の統合的保全を推進している。この取組みでは、行政・研究機関・地域住民・動物園など多様なステークホルダーを調整し、保全体制を構築するだけでなく、科学者自らが中心となって保全事業を実行している点に特色がある。個体数が急減するアカモズに対して、繁殖成功率・生存率等を組み込んだ評価を進めるとともに、それらの研究成果をもとに複数の保全計画を執筆し、補助金・交付金等を獲得し、具体的な保全策を開発することで、国や自治体を巻き込んだ保全体制を構築した。とくに2023年には、豊橋総合動植物公園との連携により、世界初となるアカモズの人工孵卵・育雛に成功し、将来的には野生復帰を視野に入れている。
このような保全事業を推進するためには、単なる「組織間の連携」ではなく、「関係者が組織の垣根を越えて、一体となって保全を進める協働」が必要である。そこで求められる成果は「優れた論文を書けたか」ではなく、「実際に対象種の個体数を回復させられたのか」、「実社会を変えられたのか」である。また、保全活動を持続可能なものとするためには、学校教育や社会教育を通じて活動の担い手を育成することも重要な使命である。このため、科学者には、科学・社会・教育に関する活動を一体化して保全を推進するための架け橋としての役割が求められる。今後も、保全の現場に立脚した科学的知見を磨き上げ、社会に根ざした実践へとつなげることで、「鳥類学」という学問が未来の自然と人との共生に貢献できることを示していきたい。
受賞者プロフィール
岡久雄二(おかひさ ゆうじ)博士(理学)。人間環境大学講師。専門は保全鳥類学。トキやアカモズなどの希少鳥類を対象に、生息域内保全と生息域外保全を統合する実践的研究に取り組む。統合個体群モデルやベイズ統計を用いた解析等により、保全政策に直結する科学的知見を提供し、多くの保全計画を執筆・策定してきた。とくにトキの野生復帰においては、育雛手法の開発や保全施策の効果検証を通じて実務面で大きな成果を挙げた。アカモズ保護増殖プロジェクトでは、地域・行政・動物園・研究機関をつなぎ、保全の推進に尽力している。普及啓発にも力を注ぎ、科学と社会をつなぐ新しい保全のあり方を実践している。
2025年度日本鳥学会黒田賞について
黒田賞は、日本の鳥学会の発展に貢献した黒田長禮・長久両博士の功績を記念して、鳥類学で優れた業績を挙げ、これからの鳥類学を担う若手・中堅会員に授与する賞である。受賞者には賞状と副賞(黒田基金及び小口基金から10万円)が授与される。
学会賞選考委員会で規定・運営指針に則して研究内容のオリジナリティ、鳥類学における重要性、将来性などについて検討、審査の上、岡久 雄二(人間環境大学環境科学部フィールド生態学科)氏を受賞候補者として理事会に推薦し、理事会の決議により受賞が承認された。
岡久雄二氏は、フィールドでの行動生態学研究から研究キャリアをスタートさせたのち、トキなどの絶滅危惧鳥類の生息域内・生息域外保全に関わり、その中で大きな役割を果たしてきた。絶滅危惧種についてのモニタリング調査を行い、得られたデータにベイズモデリングなどの統計手法を駆使することで研究を発展させている。そうした業績の一つである、放鳥後のトキ個体群についての統合個体群モデルの解析は、再導入されたトキ個体群の生存率や繁殖成功率を定量的に評価し、環境省のレッドリスト評価や報道発表の基盤データとして活用されるなど、保全政策に大きな貢献を果たしてきた。また保全活動の実践についても、さまざまな鳥種に関して組織を主導し、地域社会との協働を行いながら着実な成果をあげている。これまでに鳥学に関する36編の査読論文が国内外の学術誌に掲載されており、生息域内保全・生息域外保全の双方の領域で、フィールド調査から保全施策の評価・実践まで分野横断的に関わっている点において、岡久氏は日本において代替不可能な重要な地位を占めている。また一般誌などへの寄稿や一般向けの講演なども積極的に行い、鳥類学の普及にも大きく貢献している。こうした保全生態学の研究と実践の分野における今後の活躍がさらに期待される。
なお、受賞内容は総説として日本鳥学会の学会誌に掲載予定である。
学会賞選考委員会