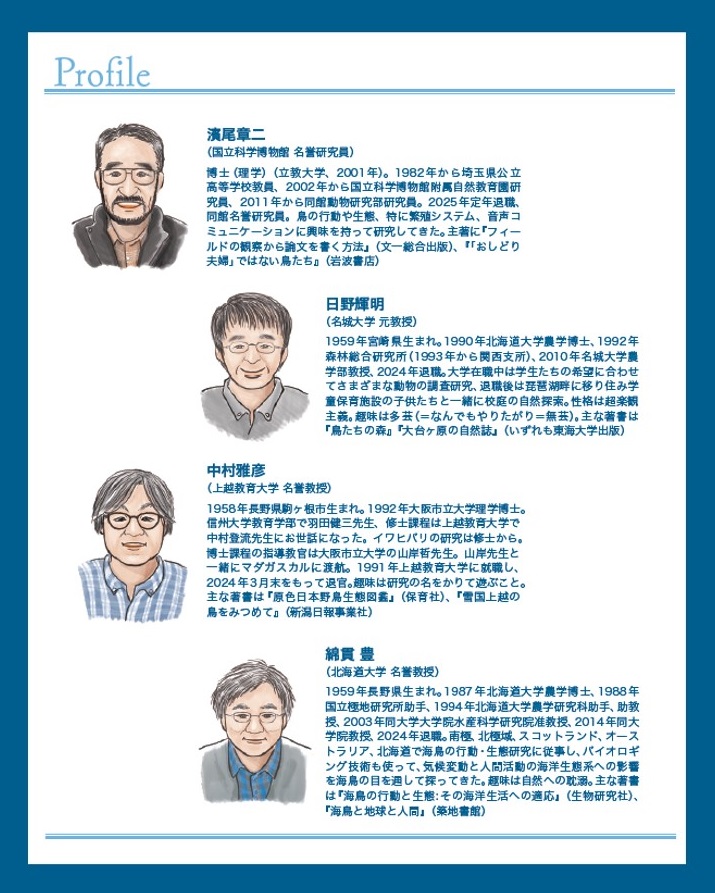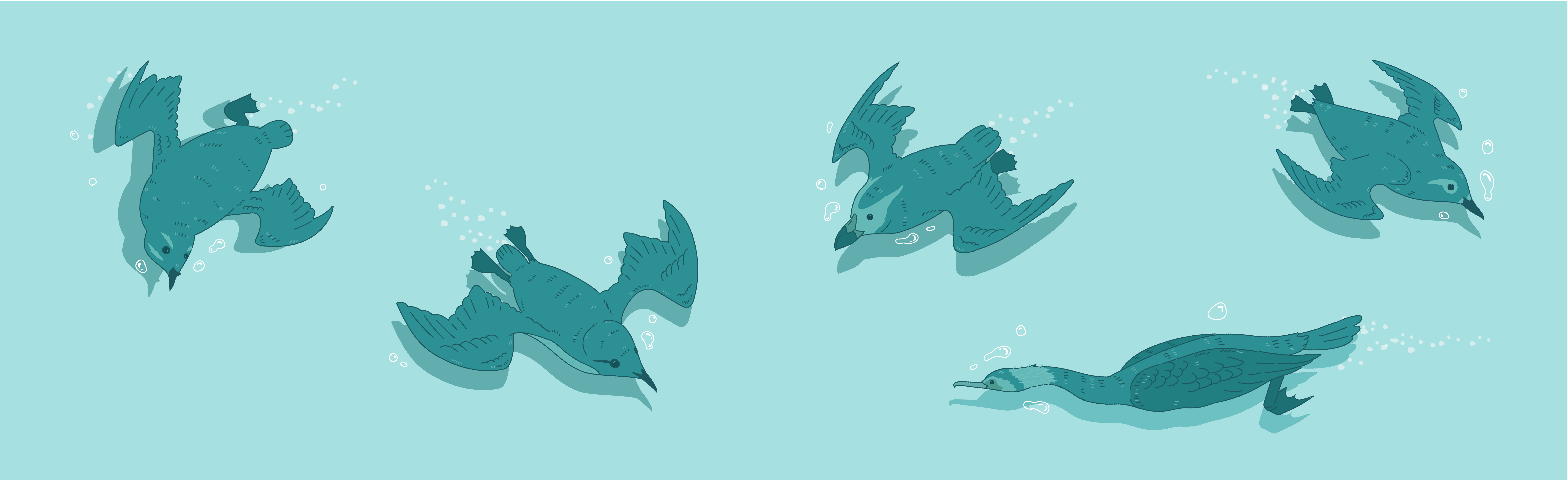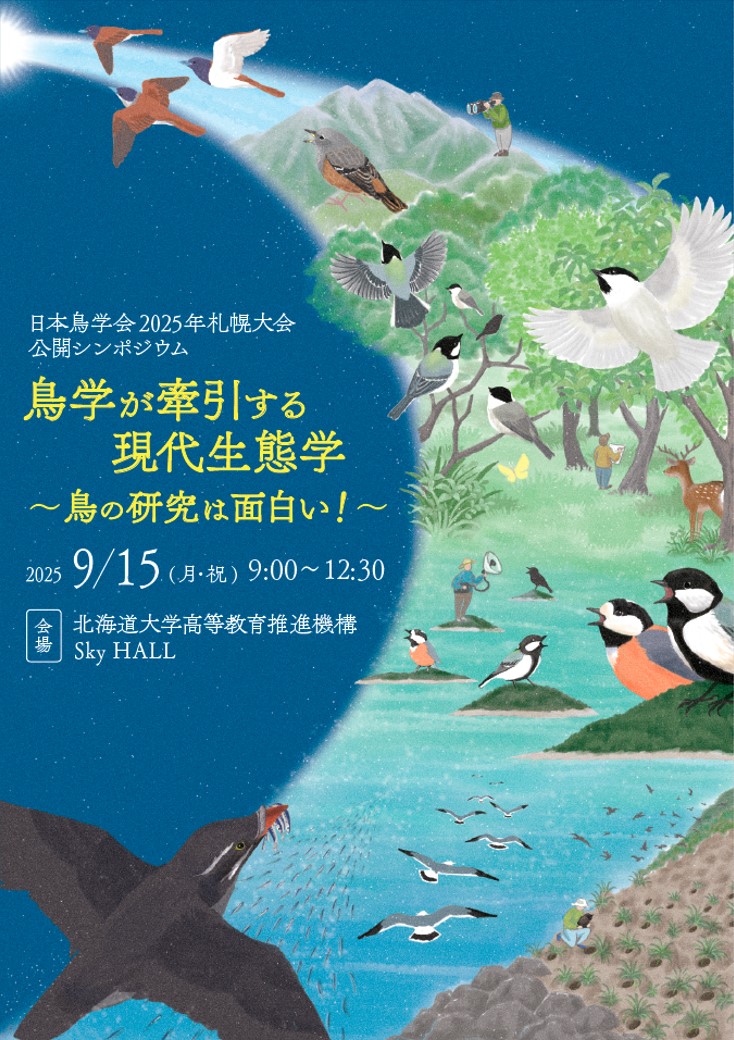
公開シンポジウム『鳥学が牽引する現代生態学~鳥の研究は面白い!~』
日時:9月15日(月・祝) 9:00–12:30
場所:北海道大学高等教育推進機構 Sky HALL(北海道札幌市北区北17条西8丁目)
この公開シンポジウムでは、鳥類を研究材料として「生態学」を牽引してこられた4人の方々にご登壇いただきます。濱尾章二さんには琉球列島におけるカラ類の近縁種が在不在の島嶼を利用した自然の実験としての「音響生態学」、日野輝明さんにはカラ類群集における個体レベルの順位制やマダガスカルの鳥類群集と大台ヶ原の研究から「群集生態学」、中村雅彦さんには高山で繰り広げられるイワヒバリの婚姻戦略やマダガスカルを舞台にした研究などから「行動生態学」、綿貫豊さんには天売島の長期研究や世界各地の研究が捉えられた「海洋生態学」です。 登壇者の皆さんには、ご自身がされてきた学術的に重要な研究を中心に、鳥を用いた研究の展望や後進へのメッセージなども交えてお話していただきます。参加者の皆さんには、鳥学が生態学にどれほど重要な示唆を与え、発展させてきたかを再確認いただき、今後も鳥学が生態学研究の中心であり続けるであろうことを実感していただきたいと思います。
プログラム
9:00-9:10 はじめに:髙木昌興(北海道大学・教授)
9:10-9:45 鳥の音声コミュニケーション-さえずりの「方言」から種認知を探る:濱尾章二(国立科学博物館・名誉研究員)
9:50-10:25 何でも屋研究者の個性とつながりの群集生態学:日野輝明(名城大学・元教授)
10:25-10:40 休憩
10:40-11:15 イワヒバリからマダガスカルの鳥へ:中村雅彦(上越教育大学・名誉教授)
11:20-11:55 気候変化への海鳥の応答を長期モニタリングとバイオロギングで明らかにする:綿貫豊(北海道大学・名誉教授)
10:55-12:05 休憩
12:05-12:30 質疑応答・パネルディスカッション
講演要旨
鳥の音声コミュニケーション-さえずりの「方言」から種認知を探る
濱尾章二(国立科学博物館・名誉研究員)
動物は、雌雄がつがいになったり同性のライバルとなわばりを争ったり、種内でさまざまな社会交渉をもつ。その際、似通った種を同種と誤認しないことが重要である。鳥類では音声を用いたコミュニケーションが発達しており、音声による種認知が行われている。しかし、オスのさえずりには地域による違い(方言)のある場合がある。よその方言を聞いた個体は、正しく同種の音声だと認知するのであろうか。そもそも、なぜ地域によってさえずりが異なるのであろうか。このような疑問に答えようと、互いに似たさえずりをもつシジュウカラとヤマガラを対象に南西諸島で研究を行った。その結果、シジュウカラはヤマガラが生息していると、誤認されぬようシジュウカラの特徴が顕著なさえずりをすること、また両種とも他方の種が生息していると種認知の基準を厳密なものにしていることが明らかとなった。音声分析と野外実験から見えてきた鳥の音声コミュニケーションの世界を紹介する。
何でも屋研究者の個性とつながりの群集生態学
日野輝明(名城大学・元教授)
群集生態学のテーマを一言で表すと「なぜその場所にはそれほど多くの種が存在するのか」となる。そのテーマを明らかにするためには、群集を構成する生きものの「個性」と生きもの間の「つながり」を明らかにする必要がある。例えば、混群を構成するシジュウカラとコガラのように外見上よく似た種であっても、エサの取り方や攻撃性・協調性がそれぞれの種の個性によって異なり、さらに、その個性の違いは同種個体間で異なる。また、群集の研究では、鳥のように特定の分類群を対象に調べる場合であっても、通常は他の分類群の生物を含めて調べることになる。例えば、エサ生物である虫たちとのつながり、生息場所を形作る植物たちとのつながり、同じ生息場所を共有するシカなどの他の分類群の動物たちとのつながりなどである。さらにまた、それらの個々のつながりは、互いにつながりあうことで間接的な影響をもたらす。このように、群集生態学では、同じ空間でともに生きるものたち間の捉えどころのない世界に挑むことになる。研究者には大きく分けると「専門家」と「何でも屋」の2つのタイプがあるが、群集生態学は後者に向いた学問なのかもしれない。
イワヒバリからマダガスカルの鳥へ
中村雅彦(上越教育大学・名誉教授)
私の鳥の研究の出発は、本州中部の高山帯に生息するイワヒバリという鳥です。最初にこの鳥を観察した時のことは今でも忘れられません。メスが、赤く腫れた自分のお尻を、オスに見せて踊っているのです。しかも、特定のオスだけでなく複数のオスに対して。普通の鳥は一夫一妻なのですが、イワヒバリは多夫多妻といって鳥の中で極めて珍しい繁殖形態をもつ鳥です。イワヒバリの形態や行動を精子競争という専門用語で説明したいと思います。
人生とはおもしろいもので、あるきっかけで世界のなかでマダガスカル島だけにすむオオハシモズ類が研究対象になりました。進化で有名なガラパゴスフィンチはすべての種が一夫一妻です。ところがオオハシモズの仲間は一夫一妻があれば、一妻多夫があり、お手伝いのいる共同繁殖もいます。私の興味はなぜ、わずか一種類の鳥がマダガスカルで複数の種に分化したのか、なぜ、多様な繁殖形態を持つようになったかです。
気候変化への海鳥の応答を長期モニタリングとバイオロギングで明らかにする
綿貫豊(北海道大学・名誉教授)
鳥類は生態系変化の指標として役に立つだろう。10年規模振動(レジームシフト)や地球温暖化さらに最近の海洋熱波など複雑な気候変化が海洋生態系を大きく変えており、海鳥の応答も興味深い。天売島のウトウは2010年までの30年間、レジームシフトとともに餌をスイッチし、雛生産はマイワシを食べた寒冷レジームでは中程度、カタクチイワシを食べた20年間におよぶ温暖レジームでは高かった。カタクチイワシ年には餌荷は重くエネルギー価も高く、近くで採食したため給餌頻度も高かったためである。その後2025年までに餌種の急変が3回見られ、寒冷性のホッケ0歳とイカナゴを食べたそれぞれ3~4年の間では雛生産が低かった。こうした短期的な餌種の変化は海洋学的にはまだ十分理解が進んでいない気候レジームの質的変化を示唆している。また連動して繁殖成績が大きく上下するのでウトウ個体群への影響にも留意しなければならないだろう。