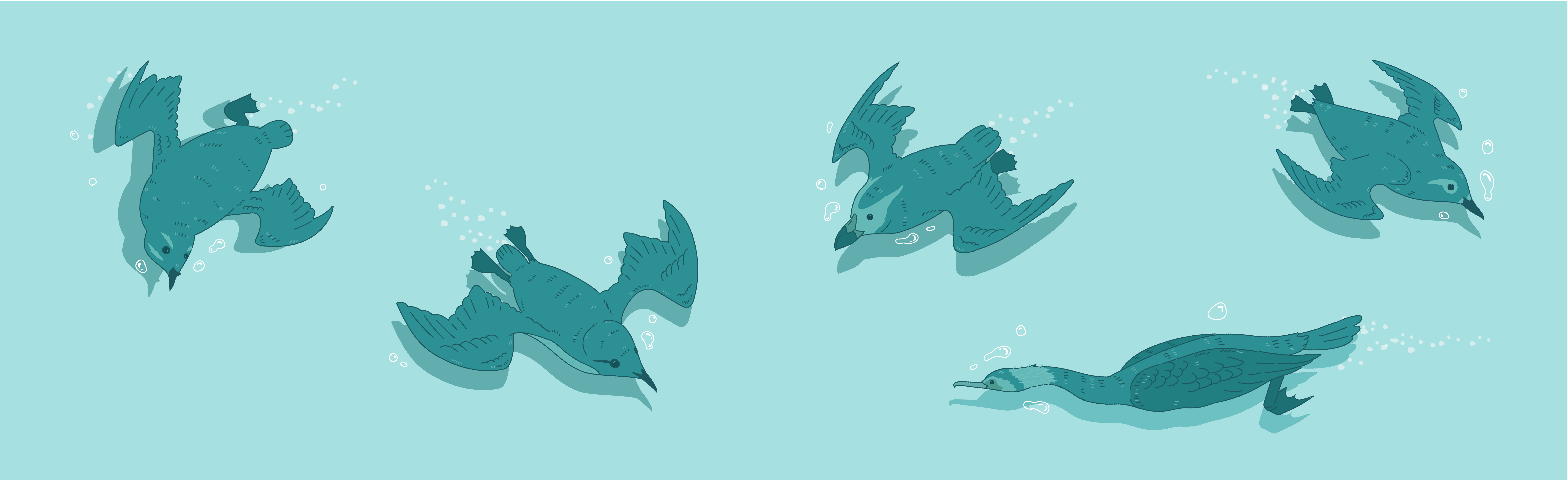企画集会
古くさい研究なんかじゃない!?インフラとして発展した鳥類標識調査の可能性を探る
企画代表者:澤 祐介(山階鳥類研究所)
日時:9月15日(月)13:45~16:45
会場:北海道大学札幌キャンパス 高等教育推進機構 N1
プログラム
13:45-14:05 インフラとしての鳥類標識調査 ~伝統的な移動データ活用からサンプ
リングを介した研究、人材育成まで~(澤 祐介:山階鳥類研究所)
14:05-14:30 標識調査で見えてきたマダニの経年変化 〜長期に渡る定点・定期調査の最大の強み〜(高野 愛:山口大学)
14:30-14:55 標識調査手法を用いた鳥類研究:蟻浴行動の進化的意義の解明について(大河原恭祐:金沢大学)
14:55-15:05 休憩
15:05-15:30 オーストンウミツバメの研究と標識調査 〜すべてはバンディングから始まった〜(寺嶋太輝:東京農工大学)
15:30-15:55 遺伝サンプリングと標識調査:鳥を扱えるからこそ取れるサンプルがある(田谷昌仁:東北大学)
15:55-16:05 標識調査への誘い:研究者、学生、アマチュアそれぞれのメリットと新たな研究インフラとしての可能性を探る(澤 祐介:山階鳥類研究所)
16:05-16:40 会場とのディスカッション
16:40 閉会の挨拶(水田 拓:山階鳥類研究所)
要旨
鳥類標識調査は日本では1924 年に始まり、日本の鳥学の発展に寄与してきた歴史のある調査のうちの一つである。「鳥類標識調査」と聞くとどのようなイメージが思い浮かぶだろうか?
・鳥に足環をつけて、移動を調べる
・個体識別して行動や個体群動態などを調べる
・長期モニタリングのひとつの手段
標識調査を単に「足環をつける調査」と捉えた場合、上記のようなイメージがまずは思い浮かぶであろう。もちろん、これは標識調査の核となる主要な内容であり、長年にわたり鳥の渡り・分散や行動生態研究、個体群動態の解明など様々な研究で成果があげられてきた。また、蓄積された膨大なデータは、過去と現在の比較研究などにも活用されてきた。しかし、標識調査でできることはこれだけだろうか?今回の企画集会では、さらなる深みを求めて標識調査を掘り下げていく。
標識調査の核となる技術のひとつに、「生きた鳥を安全に捕獲し、取り扱う技術」があげられる。近年、鳥学会の研究発表でもよく見かける発信器やロガーを用いた研究も、標識調査員(バンダー)との共同研究や、バンダーに捕獲、鳥の扱いの支援を得ているものが多く見受けられる。さらに捕獲することで、血液や羽毛、外部寄生虫、糞など様々なサンプリングが可能となり、多岐にわたる研究と組み合わせることができる。そのため標識調査はまさに、様々な研究の”インフラ”となる調査だと言えるのである。また、標識調査に携わる中で、捕獲・鳥の扱い方の技術の習得や、鳥の識別、換羽様式など鳥学の基礎的な知識を学べる他、標識調査に関わる多様な人と交流できることも大きな魅力で、自身の研究の幅を広げるきっかけを与えてくれる。この点も人材育成のインフラといえるであろう。
本企画集会では、こうした標識調査の魅力や裾野の広さを感じていただくため、5名の研究者、学生が講演を行う。最初に、標識調査の伝統的な成果である移動や長期モニタリングの活用の利点と課題について概説し、次に、標識調査を調査インフラとして活用した研究例について講演する。さらに学生の立場から、自身の研究へ標識調査をどのように活用してきたか、語っていただく。最後に、標識調査への参加方法を紹介し、標識調査に参加するメリットや今後の調査の可能性を会場と議論を交えながら考える。少しでも自身の研究と関連がありそう、標識調査に関ってみたいという方々は、ぜひ本企画集会にお越しいただきたい。
移動データを使った海鳥研究の新展開と応用
企画者:依田憲(名古屋大学)、渡辺伸一(リトルレオナルド・麻布大学)、佐藤克文(東京大学)、綿貫豊(北海道大学)
日時:9月15日(月)13:45~16:45
会場:北海道大学札幌キャンパス 高等教育推進機構 N2
プログラム
13:45-14:15 海鳥バイオロギングの最先端(依田)
14:15-14:45 海鳥の渡り経路はどこまで予測できるか?(後藤&依田)
14:45-15:15 地域スケールでの洋上風発鳥感受性マップ作製におけるバイオロギングの利用(綿貫)
15:15-15:30 休憩
15:30-16:00 オオミズナギドリを指標とした水銀汚染マップ(小田桐ほか)
16:00-16:30 BiP を用いた海鳥の移動情報の解析とデータの二次利用(渡辺&佐藤)
16:30-16:45 総合討論
要旨
日本鳥学会2009年度大会において、函館国際ホテルを会場に開催されたシンポジウム「バイオロギングによる鳥類研究」(企画:高橋晃周・依田憲)から、すでに15年という歳月が流れた。この間、バイオロギングに用いられる各種センサは多様化と小型化を遂げ、搭載可能な計測項目が飛躍的に増えたことで、研究対象となる鳥類種やテーマも拡張された。さらに、AIをはじめとした計測・解析手法の革新が加速し、収集される行動データは今やビッグデータの規模に達しつつある。また、バイオロギング研究は周辺分野との連携を急速に深化させており、新たな研究領域の開拓や、保全計画への具体的応用など、社会的要請への貢献も着実に進んでいる。本企画集会では、これまでの発展の歩みを振り返りつつ、バイオロギング研究が現在どのような段階にあるのかを俯瞰し、今後いかなる課題に取り組むべきか、そしてどのような進路を辿るべきかを多角的に再考する場としたい。